
こんにちは。我が家も一条工務店のグランスマートで家を建てて1年が経ちました。昨年の記事で触れましたが、1年間の電気代について振り返り、太陽光発電と蓄電池のコストと効果について検証してみたいと思います。

毎月電気代の報告をしているけど、光熱費が安くなったとは言え太陽光パネルや蓄電池の購入費用が高いと元も子もないよね。

全館床暖房や全館空調は快適とは言え贅沢な設備だから、導入や維持にお金が掛かるのは仕方がない事だよね。それでも少しでも節約できた金額が購入金額に近いと得した気になるよね。早速確認してみようか。
一条工務店とアパート時代の光熱費比較
まずはアパート時代の光熱費(R5年)と、現在の光熱費(R6年)を比較してみます。
R5年の10~12月はガス代の金額が記録し忘れていたため空欄となっていますが、そのままガス代はなかったものとして計算を進めます。
また、アパート時代とは言っていますが、実際に住んでいたのは築30年以上の古い鉄骨マンションの1階の中部屋に住んでいて、木造アパートや角部屋などと比べても外気の影響を受けにくいのでそこそこ快適な住環境でした。

表は左から順に今年(一条工務店戸建て)の売電収入・電気代・差引光熱費(赤字はプラス収支)、昨年(アパート時代)の合計光熱費・電気代・ガス代となっています。
5月に青字となっているのは湯沸かし器の設定を昼間に変更したタイミングです。これにより昼間の太陽光発電を自家消費できる時間帯になるべく電力消費のピークを持ってきて、夜は蓄電池のみで過ごし買電を抑える仕様にしました。
6月の青字となっているのは契約電気会社をCDエナジーからLooopでんきに切り替えたタイミングです。ここで基本料金は0円となり、純粋に使用した電気量だけの料金体系となりました。
電気代だけで比較しても全館冷房・全館床暖房を使用している今年と、使用している部屋でエアコンをON・OFFしていた昨年と電気代がほぼ変わらないことが分かります。
太陽光発電の売電収入とガス代の支払いを加味すると、その差は12万円の収益と11万8000円の支払いで24万円近いものになります。記録が漏れたガス代も考慮すれば25万円を超えるでしょう。
ここで更に考慮したいのが、床面積の差です。アパートは50平米だったのに対し、現在は100平米と倍の広さになっています。
本来は電気代もそれに伴い増加するものですが、その上でも年間25万円の差を生んでいるため、太陽光発電と蓄電池、そして高気密・高断熱の住宅性能の恩恵が数字として表れています。
1年間通して湯沸かし設定・電気会社の変更が考慮されると更に差は大きくなっていたと思われるので、また今年の6月に1年間の光熱費を確認したいと思います。
実際に使った電気量と自家消費した電気量
次に、実際に我が家で使用した電気量の内訳を確認してみます。
光熱費が安く済んでいる事は分かりましたが、太陽光発電と蓄電池の恩恵はどの程度の影響なのか。そして全館空調と全館床暖房はどれだけの電気を消費し、太陽光発電などを設置しないとどれ程の電気代となるのかを見てみます。

表の「消費」は家で消費した電力量(kwh)全体の数値になります。「買電」はその通り電力会社から電気を購入した量、「自家消費」は「消費」から「買電」を差し引いた数値、つまり太陽光発電した電気を自家消費した電気量となります。
金額換算については電力量の合計値に35円を掛けていますが、買電の合計額が前述の年間電気代とズレています。
これは我が家が契約しているLooopでんきは30分単位で電気代単価が変動し、需要に連動して電気代も変動するため一定ではないことによります。
なお、一般的な東京電力などで計算する場合には基本料金が発生するため、単純計算する場合には使用量にもよりますが1kwhあたり40円程度となります。
前置きが長くなりましたが、太陽光発電のおかげで浮いた電気代(自家消費)は約14万円となりました。
もしも太陽光発電を設置せずに全館空調・全館床暖房を使用すると、年間の電気代は20万円を超えることにります。
雪のあまり降らない関東首都圏でこの数値ですから、更に気温が下がり、雪が積もる地域では太陽光発電も性能を発揮できないため、年間の電気代は高額になるでしょう。
豪雪地域では全館床暖房の使用は推奨されない・太陽光発電も設置費用の元は取れないと考えるべきでしょう。
太陽光発電・蓄電池の設置費用は元を取れるのか
ここで気になってくるのが太陽光発電・蓄電池の費用が売電・節電で元を取れるのかという事です。
いくら収益があり、節電効果が大きいと言っても、最初の支払額が大きいと気分の問題だけで家計としては赤字になってしまう可能性があります。
アパート時代との金額差は年間25万円、1年間の売電収入と浮いた自家消費の電気代は合計32万円でした。
今年の結果が続けばすぐに設置費用250万円の元は取れそうですが、劣化率の考慮やパワコンの修繕費用も計算すると赤字にならないのか。
次回の記事では卒FITや劣化率も考慮した10年・15年の収益も計算してみたいと思います。
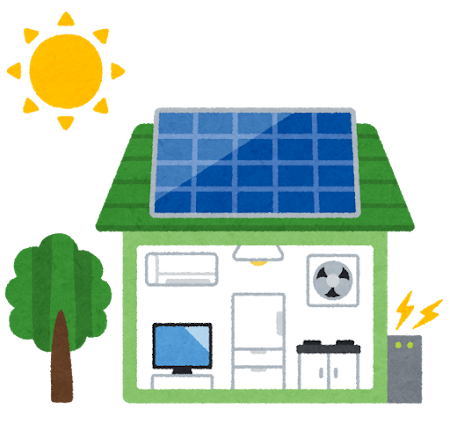


コメント